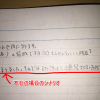吃音者にとっては言葉を発することは基本的にはすべて苦手だ。
そして大勢の前で話すのは大げさではなくて地獄の思いだったりもする。
大勢の基準は吃音者によっても違うだろうが、中学生当時の僕にとっての大勢は、やはり1クラスだったと思う。
その大勢の中でも話すことをさけられないのが教科書の朗読である。
今でこそ、>>この教材<<で、どもりを克服した上にフィリピン移住を果すという、まるで人生大逆転かと思うような日常を送っている僕だが、多感なこの頃は、毎日、何かしらの試練が待ち構えていた。
その一つが、これからお話することだ。
朗読という強制執行
今思い出してもゾクッとすること。それが中学校の授業での朗読。
どこからとなく先生が指名するその日のスタート地点。
一人ひとりの順番が回ってくる思いは、さしづめ死刑執行の順番待ちのような気持ちだった当時の僕。
朗読というシステムは吃音者にとっては実に不合理なシステムであった。
当然、どもりグセのある僕は朗読のある授業は苦戦した。いまこの回顧録を書き始めた時は国語の授業のことを思い出していたのだが、そう、朗読だからといって必ずしも国語とは限らないのだ。
そんな授業での教科書朗読。
当然、はじめは頭から火が出るほど(今と違って火元である髪の毛はふんだんにあった)恥ずかしかったし緊張もしまくりだったのだが、実は、この教科書朗読については、かなり克服に近い感触を中学校時代から得ていたのだ。
ドラマ仕立ての聴かせる朗読
ヒントはカラオケだ。
小さい時から8トラック(通称エイトラ)という特殊なカセットテープみたいなカラオケ機器が自宅にあるほど、うちはカラオケ好きな一家だった。
だからかどうかはわからないが、僕が声を発する時に唯一どもらないのがカラオケをする時だったのだ。
なぜカラオケでどもらないのかは不明。
ただ2つだけポイントを感じていた。
ひとつはリズムや音楽というもの。
カラオケは音楽に乗せて言葉を発するもの(歌うもの)だから吃音が出ないのだと思った。
単語と単語。文節文節が音楽のメロディーになめらかに乗って行くのだろう。
そしてポイントの二つ目は抑揚。
感情を表現して抑揚をつけると吃音が出にくいのではという仮説だ。
これについては感情が出るものならなんでもいいというわけではない。
その証拠に経験上、感情的になって相手と口論をするときなどは逆にどもりがひどくなったりする。
あくまでも一方的な感情の起伏ではなくて、抑揚でリズミカルに読むことを意識した時に吃音を防げるということがわかったのだ。
具体的にどういうふうに読むかというと、ドラマのセリフのように読む。
なので中学校の頃の僕の朗読はちょっとしたセリフの読み合わせ稽古みたいだったと思う。
吃音者が朗読でどもるのを克服した瞬間だ。
ただし朗読でのどもりを克服したのと同時に、代償を支払う羽目になったことも事実。
それは・・・
セリフのような読み方がクラスメートには特殊に感じ、クスクス笑われたこと。
とはいえ、先生には基本的にほめられるような視線を送られるので、吃音が出てしまって笑われるよりはよっぽどマシだと思った。
ちなみに朗読というと、結構つっかえる人も多いが、このセリフ朗読法はそれも軽減される。
とにかく、吃音者の僕が、どもりが出ないのはもちろんのこと、ほとんどつっかえないで読めるのである。
克服法を発見した時は密かに嬉しかった。
なぜ小学校ではなくて中学校?
ここまで書いてきて思ったのだが、なぜ「中学校の授業」での朗読を思い出したのだろう?
たしか小学校でも朗読はやっていたはずなのに、なぜ中学校だけ?
はっきりとした答えはもちろんわからないのだけれど、おそらく中学校でのどもりは異性を意識しだした頃だったので、女の子に対する恥ずかしさがそのまま印象に残ったのだろうという結論に達した。