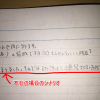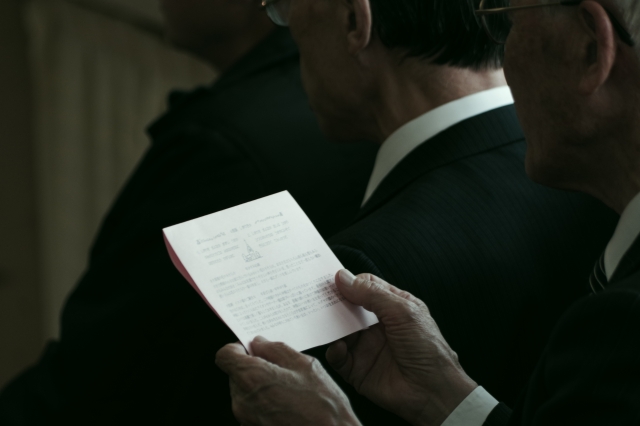
あれは新卒で建設会社に入って2年目の冬だった。
珍しくお袋から携帯に電話が入る。
時は1997年、ようやく個人が携帯電話を持ち始めた頃だった。
当然、お袋は携帯なんて持っていないので、自宅の電話からだ。
母:「O君から手紙が来てるよ。」
当時、僕は神奈川にある会社の寮に入っていたが、建設業という仕事柄、いつどこに現場が変わるかわからないので、かなり親しい友だちにも居場所は伝えていなかった。
必然的に年賀状その他の郵便物は、基本的に実家のほうに送られてくる。
しかし、Oから?
もちろん大学時代の親友は親友なんだが手紙なんて送り合うような間柄ではない。ましてや野郎同氏で・・・
その時点で僕はピンときた。
彼から届いた両家の名入りの手紙
Oとは大学でサークルが同じだったのだが、その一つ下の学年にOの彼女はいた。
実はOも建設業で働いていて、就職してからはお互いに年1回位しか会うことはなかった。
とはいえ、会う時はその彼女も連れてきていたし、まだ付き合っているようだった。
なので・・・
僕はお袋に尋ねた。
僕:「なんて書いてあるの?」
開けて居るわけはないのだが、外観でなんとなくわかるだろう。
母:「たぶん結婚式の招待状だね。両家の名前が書いてあるから」
親友の結婚式、なんの依存もなく参加することにした。
しかし、吃音者にとっての結婚式は他の人とは意味合いが違う。
吃音者にとっての難関
いや、正確にいえば、特に親友でもないやつの結婚式に参加したところで困ったことはない。
唯一の難点といえば、新婦側の友達とスムーズにコミュニケーションが取れないことくらいだろうか。
もちろん吃音が出てしまい、恥ずかしくて会話が成り立たないからだ。
そんな時僕は、決まってつまらない奴になる。
招待状の「ご出席」に丸をして返信してから程なくして、Oから直接電話があった。
年に1~2回は会うわけだし、携帯の電話は伝えてあったのだ。
そこで彼は当然のようにこう話した。
O:「友人代表で頼むよ、スピーチ。Kにも頼んであるから、二人で。」
恐るべきことが来てしまった。
まあ親友なんだし、結婚式のスピーチを頼まれなければ頼まれないで、それはまた寂しいもんだが、確実にプレッシャーはかかってくる。
それでもスピーチ、やるしかない。友人の幸せを祝して・・・
どうしても読みたくはなかった
1997年4月下旬、港の割には風は強くなく、陽光きらめく春の日だった。
そこでは新婦かっての願いだった洋上結婚式の舞台が整っていた。
横浜は大さん橋、そこにはクルーズ船 ロイヤルウィングが停まっていた。
華やかな舞台にみな吸い込まれるように乗船していく。
僕もやはり学生の頃から付き合っていた彼女と二人で入場していった。
僕の彼女は、新婦の先輩であり、新郎の同級生でもあるのだ。
「次は結城たちの番だね☆」
なんて、いろいろな人に言われつつ、ついに出番がやってきた。
先にKがしゃべる。そして僕。
吃音者なら誰しもわかると思うが、読み物があるとセリフみたいに感じて少しはどもりが軽減される。
すくなくとも僕はそうだった。
もちろん僕も、スピーチのスクリプトを用意していた。
読んでも良かったと思う。別に誰も気にしないと思う。
でもそれを僕はしたくなかった。
親友への餞(はなむけ)の言葉を単なるスピーチで終わらせたくはなかったというのもある。
読んだらセリフ、書いたものを覚えて話したらスピーチ。
心からその場で発した言葉で伝えられれば、それは真の餞の言葉。
しかし、その代償は大きかった。
緊張を抑えるために、結婚式序盤からかなりのハイペースで酒を飲んでいたのだ。
<飲めば話せる>
そんな愚策に走ったあの頃が懐かしい。
その夜は、当時の彼女と、磯子にある横浜プリンスホテルに宿を取った。
3次会まであったので結局ホテルに着いたのは朝の3時。
チェックアウトまでの一時のあいだ、彼女と将来を語りあ・・・えずに熟睡してしまったのはいうまでもない。
Oは3人子供が出来、未だ幸せだ。僕と当時のカノジョはそのあと結局別れてしまった。
横浜プリンスホテルでぐでんぐでんに酔っ払ってても夜毎将来について語り合っていたら、カノジョと結婚していただのだろうか・・・
そんなことはともかく、実際に結婚してしまったOと、そのかみさんのCちゃんには末永く幸せでいて欲しい。